世の中の大半の医師は、臨床医として勤務しています。昼夜問わず働き、自分や家族の時間も犠牲にしている医師は多く、何かしらの不満を持っている方も多いのではないかと思います。
しかし、何十年と臨床医を続けている理由はなぜでしょうか。
「やりがいのある仕事だから」とか、「収入が安定しているから」という理由を挙げる医師が多いのではないでしょうか。あるいは、「医師免許を持っているから」と答える医師もいるかもしれません。
医師国家試験に合格して医師免許を取得したら、臨床医として働くものである、といわれればそうかもしれません。
大学卒業後、大部分の医師は2年間の初期臨床研修を修了します。その時点で臨床業務に慣れてきて仕事として魅力を感じ、そのまま臨床医を続けているケースが多いと思われます。
でも医師免許があっても臨床医として働く義務があるわけではありません。
こんなことをいうと、「何を言っているのだ、医業以外は邪道である」と考える医師もいるのではないかと思います。
そのご意見は至極当然です。なぜなら、医師免許がないと、医療行為を行うことができないため、その免許を持った人が臨床医として働かなければ、病気で困っている患者さんを救うことができないからです。医学教育に税金が投入されているという現状もあります。
これらの事情は承知の上で、話を進めていきます。この記事の趣旨は、あくまでも臨床医以外の働き方を考察するものであり、決して転職を勧めているわけでありません。
転職という選択肢を考えたことのない医師も多いのではないか、そのような医師に向けて臨床医以外の選択肢があることを紹介する価値はあるのではないか、と思って書き連ねています。
臨床以外の職場でも、医師免許を持っていることを強みに働くことができる

なぜ自分が医師になったか、という理由を振り返って考えてみると、おそらく、病院やクリニックなどで働く医師に憧れて、医学部で勉強して医師になったケースが多いのではないかと想像します。あるいは、親族が営むクリニックを継承するために医師になったというケースもあるでしょう。
多くの臨床医は、臨床以外で働いてみよう、という考えを持ったことが少ないのではないでしょうか。しかし、2030年頃には医師が過剰になる状況に直面するといわれています。そのとき、臨床医以外での働き方も選択肢に入ってくるかもしれません。
調べてみると、意外なほどに医師免許を持っていても臨床以外で活躍している人は多くいるのです。
彼らの多くは医師免許を持っていることを強みに他業種で活躍しています。
病院やクリニック以外でも、医師免許があるということは大きな参入障壁となり、医師であるというだけでとても大きな武器になるのです。
これから紹介するいずれの職種も、当直やオンコールなど、いつでも呼び出される状況は原則的になしで働くことができるということが、病院勤務医との大きな違いになります。
意外なほどに選択肢は多い!医師が臨床以外で働く職種
- 研究医・法医学
- 公務員
- 政治家
- 弁護士
- 保険会社・製薬会社
- 健診医・産業医
- 施設医
- 公衆衛生医
- タレント・芸能人
- 作家・漫画家
- 医療系ベンチャー起業
- コンサルタント
・研究医、法医学
大学や研究機関で研究に従事します。大学の場合、教員として学生教育も行いますが、興味のある研究に没頭できる楽しみがあります。副業として定期的な医師バイトも行っている医師も多くみられます。

・公務員
医師としての経験を生かす公務員の業務としては、医系技官と矯正医官、都道府県の保健部長や保健所長があります。
○医系技官は厚生労働省が勤務先になります。
中途採用も可能ですが、卒後3年目の入省が多いようです。公衆衛生分野で活躍することが可能で、政策立案によってより良い医療を目指すことに関与することができます。
数年間勤務後に臨床に戻ったり、起業したりする人も多く見られます。
○矯正医官は法務省が勤務先になります。
刑務所や拘置所、少年院などで医師として働きます。
募集サイトによると、国家公務員の医師ではありますが、兼業の特例が認められています。
http://www.moj.go.jp/KYOUSEI/SAIYO/index.html
・政治家
国会議員だけでなく地方自治体の県議や市議など、医師の議員はそれなりに存在します。医師個人では難しいことも、議員の立場になることでより良い医療の政策づくりに寄与できるという貢献が可能です。
・弁護士
医療過誤訴訟が増えるに従い、医療に詳しい弁護士のニーズが高まっています。弁護士資格を取得する医師も増えてきています。
・保険会社、製薬会社

保険会社では、加入審査業務や保険査定業務など行うことがあります。
製薬会社では、医学的な見地から製薬会社内の業務に携わる医師(メディカルドクター)がいます。新薬開発時の治験データ分析や、厚生労働省に申請する書類の評価、市販後調査などの業務を行います(https://www.elite-network.co.jp/dictionary/md.html)。
・健診医、産業医
産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う医師です。労働安全衛生法によって、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています(https://jmaqc.jp/sang/occupational_physician/)。
臨床と掛け持ちで学校医などを行っているケースと、企業の専業産業医というケースがあります。
産業医の業務は、企業で働く労働者の健康を増進することで、内科的な知識に留まらず精神科的な知識も生かす必要があります。
産業医になるためには、以下のいずれかの要件をクリアし、資格を得る必要があります。
- 日本医師会認定産業医制度で規定された所定の研修を修了している(5年毎の更新)
- 産業医科大学の産業医学基本講座を修了している
- 産業医科大学で該当課程を修了し、卒業し、大学が行う実習を履修している
- 労働衛生コンサルタント試験(区分:保健衛生)に合格している
- 大学の公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師の経験者
・施設医
介護老人保健施設などで、主に入居者の健康管理と治療を担います。入居者一人一人とじっくり向き合うことができるのが、施設医の仕事の魅力になります。勤務医として働く場合や施設長として施設運営にも携わる場合があります。
求人内容によりますが、一般の病院勤務よりも高給であったり、時間外労働はほとんどなかったりする場合があります。今後団塊の世代の高齢化に伴って、需要が高まっていくことが予想されます。
・公衆衛生医
保健所長や都道府県の福祉部などで、地域の公衆衛生業務を担います。採用枠はかなり限られていることからタイミング次第の就職となりやすいです。
・タレント/芸能人
テレビやネット配信などのメディアで活躍する医師もいます。事務所に所属して専門家やタレント・芸人として出演したり、Youtubeなどで自ら配信することがあります。
あくまでも本業は医師で、副業で芸能活動を行っているケースが多いと思われます。
・作家、漫画家
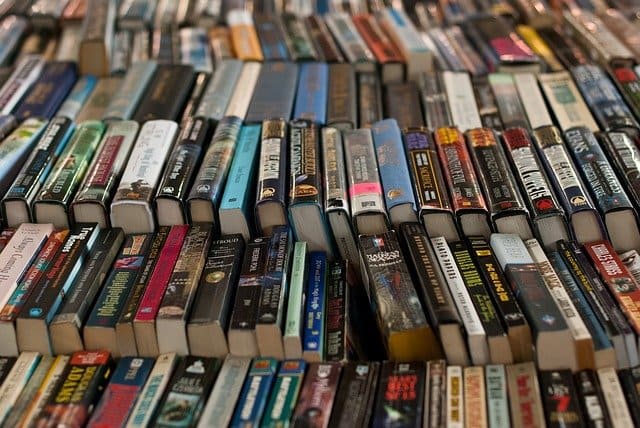
漫画家の重鎮としては、手塚治虫氏が有名ですが、現役医師で漫画家として活躍されている方もいます。また、作家では渡辺淳一氏や海堂尊氏などが有名ですが、他の現役医師でも多数の小説家の方がいます。
これは才能がないと難しいかもしれませんが、論文を書いたり、スケッチを書いたりする医師にとっては、親和性のある業界なのかもしれません。
・医療系ベンチャーなどの起業
近年、ヘルスケア業界で起業する医師も多くなってきました。
具体的な社名は控えますが、電子カルテ開発、AI問診システム、医療情報メディア、オンデマンド往診、オンライン診療、治療アプリ開発、人材派遣・ネットワーク、遠隔医療相談、医療画像診断など、さまざまなニーズに応えている会社があります。これは2015年以降明らかに増えている状況です。(https://jomdd.com/2018/01/1596.html、https://note.com/aritaku/n/n5ccbfbc2e0a0)
医師がCEOであることで、臨床業務の経験や医師としての人脈などを生かし、会社が急成長しているということが推測されます。
待遇は企業によるところですが、製品開発したものがヒットすると大きく利益を得られる夢のある仕事です。
・コンサルタント
医療系コンサルタントとして、企業経営や開業支援などに協力します。
クライアント側にとっては、実際に臨床医を経験しているコンサルタントであることが大きな信頼感につながるという理由で、採用しているケースも少なくありません。
実際に転職をするには

・転職の目的を定めることが、最も重要
転職する場合は、転職の目的を明確にすることが最も大切です。毎日が辛いから、という理由だけで、目的がはっきりしていない場合は要注意です。
何らかのストレスを抱えて、こんなことになるなんて…、と後悔してしまう可能性も高くなるので、最優先されることは目的の設定です。
・どのように転職することを決める?決断に至るまでに必要なマインドとは?
転職の目的を決めるには、現状の問題点や理想・目標などを整理することをお勧めします。満足している点と不満に感じる点、何年後までに叶えたいこと、など書き出してみるのです。
人生の転換点になるかもしれないため、自分だけではなく、家族と相談すると良いと思います。
現状を続けていて理想や目標に到達しそうであれば、そのまま日々の生活を続けていれば良いと思います。現状のままでは将来が明るくならないと考えるのであれば、その時点で、どうすれば打破できるのか、考えることになります。
働き方を変えれば良さそうな課題を抱えているのであれば、転職という選択肢が生まれてくると思います。ただ、転職で全ては解決されませんし、失うものもあるでしょう。
これまでその組織内で積み上げてきたキャリアを捨てることになるかもしれません。転職先によっては、社会的な地位が下がったことを痛感することもあるかもしれませんし、周りの目も気になるかもしれません。
しかし、「年収はそれほど変わらないけれど、理想のワークライフバランスに近づいた」とか、「自分の趣味の時間が増えた」とか、「チャレンジしたかった夢を叶えられた」など、替えがたい経験を得られる可能性もあります。
また、ある程度の時間が経った時点で、思い直して、再度臨床医に戻ることも不可能ではありません。もちろん、継続的に診療業務をしていない分、以前と同じ条件では難しいことが予想されますが、医学や医療の分野は常に進歩していくため、最新の知識を常に勉強し続けることが、その準備につながるでしょう。
自己分析も必要です。自分の強みや弱みを把握していると、希望に近い転職先を見つけられる手がかりにもなります。
転職の時期やタイミングはいつが良いか

医師の退局や退職はおおよそ6ヶ月前から上司に辞意を伝えることが多いと思われます。担当している患者さんの申し送りなども必要になるため、病院側には少なくとも3ヶ月前までには伝えないと迷惑がかかってしまいます。
いつから転職の計画を立てるかは自由ですが、何年も先の計画では気持ちが持たなくなる可能性もあります。何か区切りになるような時期がないのであれば、長くても1年以内で考えていくのが現実的ではないでしょうか。
起業は自分の都合で進めて良いでしょうし、公務員の入職募集は毎年決まった時期に行われていますが、他の転職先の多くは先方の都合になると思います。自分の力だけで動くことが難しければ、転職支援会社を利用することも選択肢となるでしょう。
まとめ
転職はメリットとデメリットを十分に考慮した上で決断しましょう。目的を設定して、現状の把握と自己分析を行なって転職を考えていく、というこの段階を経て動き出すのであれば、転職が失敗に終わる確率が限りなく低くなると考えられます。
